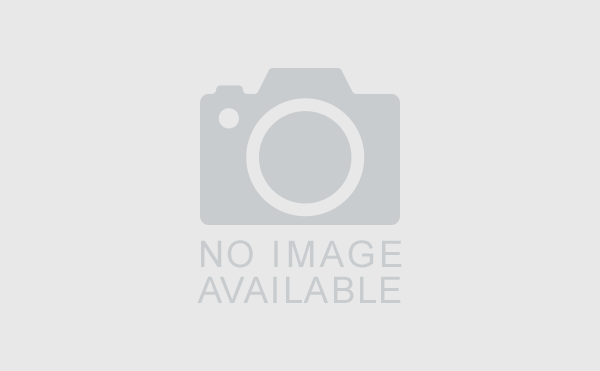天保12年(1841年)創業。
醤油発祥の地、紀州・湯浅で鎌倉時代より、750有余年にわたって受け継がれてきた
伝統の醸造法を現在に伝える湯浅で唯一の手づくり醤油の醸造蔵です。

| 所在地 | 〒643-0004 和歌山県有田郡湯浅町湯浅7 |
| TEL | 0737-62-2035 |
| 営業時間 | 9時~17時 |
| アクセス | 和歌山ICから約25分 |
| 駐車場 | あり |
| ホームページ | https://www.kadocho.co.jp/index.htm |
醤油資料館・職人蔵
醤油資料館・職人蔵の見学が可能。
醤油資料館ではジオラマやパネル等で醤油づくりをわかりやすく紹介されています。
展示している道具は全て実際に醤油醸造に使われたもので、
職人蔵の見学ご希望の方は、醤油資料館にて醤油の製造法等を映像で見ていただけます。
また、2022年12月には幕末から明治にかけて建てられた醤油蔵など
11棟の建物が国の重要文化財へ指定されました。


角長の醤油
徹底した手づくり・長期熟成: 天保12年(1841年)の創業以来、機械に頼らず、職人の手によって丁寧に造られています。大豆と小麦、塩を厳選し、冬季のみに仕込む「寒仕込み」を守り、約1年半という長期にわたって吉野杉の木桶でじっくりと天然醸造されます。
蔵つき酵母(くらつきこうぼ)の力: 創業当時から使われている蔵の天井や梁には、醤油造りに不可欠な「蔵つき酵母」が住み着いています。
この蔵独自の酵母が、角長醤油の濃厚で深い旨味と柔らかな香りを生み出す最大の秘訣です。
代表的な商品「濁り醤(にごりびしお)」: 特に有名なのが、「濁り醤」です。
これは、もろみから自然に溜まった汁を、圧搾も加熱(火入れ)もせずにすくい取った生醤油で、人の手を一切加えていません。
そのため、一般的な醤油とは異なる、麹の旨味がそのまま詰まった濃厚で芳醇な風味が楽しめます。
味わい: 化学調味料や保存料は一切使用しておらず、琥珀色でつやがあり、食材の風味を引き立てる濃厚で優しい味わいが特徴です。
特に、脂の乗った刺身や、熱々のごはんに少し垂らして香りを味わうのに最適とされています。